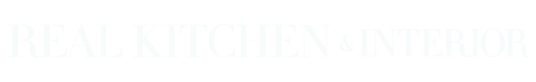個人事業主に興味はあるものの漠然としたイメージしか持てず、詳しいメリット・デメリットや、フリーランスとどのような違いがあるのかを知りたい方もいるでしょう。個人事業主の意味やフリーランスとの相違点、メリット、求められる手続きなどを解説します。
目次
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人のことを指します。
副業として始める会社員も多く、開業届だけでスタートできる手軽さが魅力です。この記事では、個人事業主の意味や法人・フリーランスとの違い、メリットやデメリットについてわかりやすく解説します。
個人事業主とは
 個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことを指し、税務上の区分の1つです。従業員を雇用していても法人を設立していなければ、個人事業主に該当します。
個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことを指し、税務上の区分の1つです。従業員を雇用していても法人を設立していなければ、個人事業主に該当します。
事業とみなされるかどうかについて、明確な基準はありません。しかし、一般的に以下のような点から総合的に判断されます。
- 経済活動は継続的、反復的か
- 営利性を伴うか
- 独立性が認められているか
- 対価性が存在するか
上記のような判断基準に基づき、営んでいるビジネスが事業と認められれば、それが会社員の副業であっても個人事業主となります。
参考:デジタル大辞泉
■フリーランスとの違い
「フリーランス」は、特定の会社や組織に属せずに業務を行う「働き方」を意味する言葉です。個人事業主は税務上の区分であるため、そもそもの概念や定義が異なるといえるでしょう。
つまり、働き方という観点からは、個人事業主もフリーランスに含まれます。ただし、フリーランスは働き方を意味する言葉であるため、法人も含まれることに注意しましょう。
参考:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
■法人との違い
法人とは、法律によって個人と同じように権利や義務を持つ、資格や人格を与えられた組織や団体のことです。法人に与えられる人格は、法人格と呼ばれます。法人化するためには、一定の資金や法務局での登記などが必要です。
一方、個人事業主は、法人を設立せずに事業を営む個人を指します。
参考:デジタル大辞泉
個人事業主のメリット
 個人事業主になることで得られる主なメリットは、以下の7点です。
個人事業主になることで得られる主なメリットは、以下の7点です。
- 自由な働き方ができる
- 成果を上げれば収入を増やせる
- 定年がない
- 簡単な手続きで事業を開始できる
- 税務申告が比較的簡単にできる
- 青色申告特別控除が受けられる
- 必要経費を計上できる
それぞれの内容を解説します。
■自由な働き方ができる
個人事業主は、会社員と比べると自由な働き方ができる傾向にあります。会社員の働く場所や時間は、就業規則によって定められていることが一般的です。しかし、個人事業主は、働く場所や時間を自分で決められます。
また、受ける仕事を自分で選別することも可能です。店舗を運営する場合は、定休日や営業時間も自分で決めます。
■成果を上げれば収入を増やせる
成果を上げた分、収入を増やせることも個人事業主のメリットです。会社員の場合、短期間で昇給すること自体がレアケースであるうえ、決められた給与体系が存在することが多く、昇給にも限界があるといえるでしょう。
しかし、個人事業主には決められた給与ランクがないため、自分のスキルや努力、ビジネスモデル次第で上限なく収入を伸ばすことも可能です。
■定年がない
定年がないことも、個人事業主のメリットの1つです。一定の年齢でリタイアする個人事業主もいますが、会社員とは違い、自分で引退のタイミングを決められます。
会社員については、たとえば65歳で定年退職をした後、新たに仕事を探すことは簡単ではありません。一方、健康寿命は上昇しています。個人事業主として働いていれば、一般的に定年退職を迎える年齢になっても新たに仕事を探す必要がなく、収入を得られます。
■簡単な手続きで事業を開始できる
個人事業主は、簡単な手続きで事業を開始できます。法人の場合、設立には登記申請が必要であり、最低でも「定款認証費用5万円」と「登録免許税15万円」の合計20万円がかかります。
しかし、個人事業主になるのに必要な手続きは、所轄の税務署への開業届の提出のみであり、登記費用もかかりません。
■税務申告が比較的簡単にできる
個人事業主は、確定申告が比較的簡単にできることも特徴です。法人の税務申告は、正確性が非常に大切です。そのため、税金の計算や帳簿付けを税理士に依頼するケースも多くみられます。
個人事業主の税務申告は、会計ソフトを使うことで比較的簡単に行えます。
■青色申告特別控除が受けられる
個人事業主になるメリットとして、青色申告特別控除の対象になることも挙げられるでしょう。
個人事業主の所得税の申告方法には、白色申告と青色申告があります。青色申告は、税制上の優遇措置を受けられる制度です。原則として事業の取引を複式簿記によって記録しなければならず、白色申告よりもやや複雑で手間がかかるものの、電子申告等と合わせて最大で65万円までの控除が受けられます。
参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
■必要経費を計上できる
必要経費を計上して節税できることも、個人事業主のメリットです。必要経費とは、事業活動を行うために必要な費用のことです。
個人事業主が納める所得税は、売上から経費を差し引いた残りの「事業所得」に課税されます。事業に必要な出費を経費と計上することで、課税対象となる事業所得額を抑えられるため、節税ができます。
事業にかかわる経費として認められる費用であれば、上限なく計上することが可能です。ただし、売上に対して著しく多額の経費を計上すると、税務署から脱税などの疑いをかけられるリスクがあることに注意しましょう。
参考:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
個人事業主のデメリット
 メリットの多い個人事業主ですが、以下のようないくつかのデメリットも存在します。
メリットの多い個人事業主ですが、以下のようないくつかのデメリットも存在します。
- 法人と比較して社会的信用度が低い
- 収入が不安定になりやすい
- 融資に通りにくい
- 社会保険に加入できない
- 一定額を超えると法人よりも税率が高い
それぞれの内容を解説します。
■法人と比較して社会的信用度が低い
個人事業主は、法人と比べて社会的信用を得にくい傾向があります。法人は、会社法などの法律に基づいて運営されることから、取引先や金融機関からの評価を得やすいとされています。そのため、銀行融資の審査も法人の方が通りやすい傾向にあるといえるでしょう。
一方、個人事業主は法人に比べて社会的な信用度がやや低く、企業によっては取引を敬遠されるケースもあることを知っておきましょう。
■収入が不安定になりやすい
個人事業主のデメリットとして、収入が不安定になりやすい点も挙げられるでしょう。基本的に会社員は、毎月決まった給料が支払われます。
しかし、個人事業主は利益を出さなければ収入を得られません。業績によっては収入が大幅に減少してしまいます。開業直後は顧客が安定せず、収入が不安定になってしまうことも珍しくありません。
案件を獲得するためには、人脈を広げたり営業活動をしたりするなど、仕事を継続するための努力が求められます。
■融資に通りにくい
融資に通りにくいことも、個人事業主のデメリットの1つです。個人事業主は、事業用の資金と生活費の境目が曖昧になりやすく、事業用の資金を適切に運用しているかどうか可視化しにくいため、融資審査で不利になってしまう傾向があります。
ただし、事業用と生活用で口座を切り分け、利益計上を行い納税義務を果たしていれば、個人事業主であっても融資を受けられる可能性が高まるでしょう。
■社会保険に加入できない
個人事業主は、社会保険に加入できない点もデメリットです。厚生年金保険や健康保険などの社会保険に加入できない分、将来的に受け取れる年金額は少なくなってしまいます。
さらに、会社員が病気やケガで働けなくなったときに使える傷病手当金制度のような仕組みも存在しません。
貯蓄をしたり、小規模事業の経営者を対象とした退職金制度である小規模企業共済に加入したりするなど、自分自身で将来に備えておく必要があります。
■一定額を超えると法人よりも税率が高い
個人事業主の事業所得が一定額を超えると、法人の税額を上回ってしまう点にも注意しましょう。個人事業主には所得税が課せられ、所得税は「累進課税制度」の仕組みによって所得額の大きさに応じて税率が高くなり、最大税率は45%です。
一方、法人に課せられる法人税は「比例課税制度」の仕組みによって、一部を除き所得額にかかわらず一律の税率が適用され、最大税率は23.2%です。したがって、個人事業主の年間の事業所得が700〜800万円を超えたら法人化を検討することをおすすめします。
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
会社員が副業で個人事業主になるには?
 会社員が副業で個人事業主になるには、まず勤務先の会社が副業を認めているかどうかの確認が必要です。副業自体は認められていても、一定の範囲内のみ認めるというケースも少なくありません。その場合、認められた範囲内に収まっているかをしっかりと検討しましょう。
会社員が副業で個人事業主になるには、まず勤務先の会社が副業を認めているかどうかの確認が必要です。副業自体は認められていても、一定の範囲内のみ認めるというケースも少なくありません。その場合、認められた範囲内に収まっているかをしっかりと検討しましょう。
また、個人事業主が事業を営んで収入を得た場合、その利益は事業所得になります。個人事業主になるためには、事業から得る利益が事業所得である必要があり、会社員が副業で行う事業が事業所得として認められるのは、以下のような要件を満たす場合です。
- 営利性や有償性がある
- 反復性や継続性がある
- 独立性や自己責任制がある
- 時間と労力の投下がある















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE